- トップ
- 一問一答 消費者裁判手続特例法
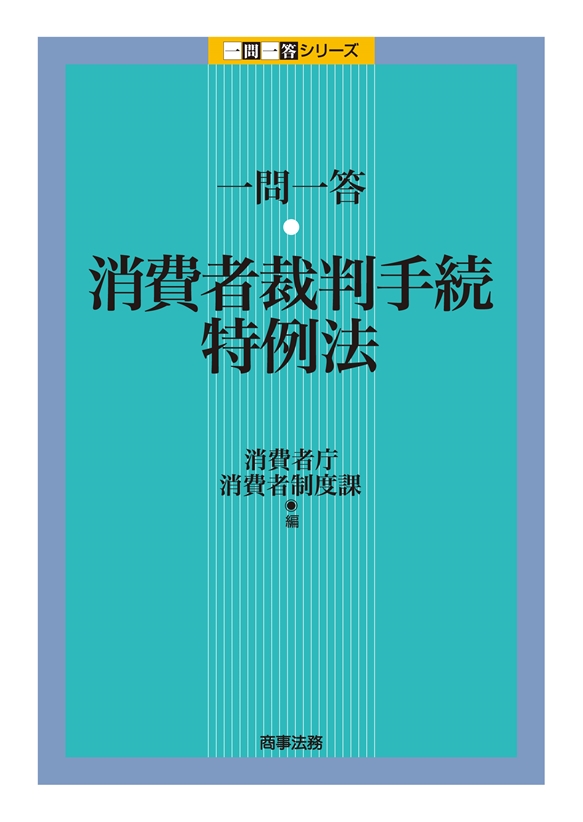
一問一答 消費者裁判手続特例法
消費者庁消費者制度課 編
A5判並/290頁
ISBN:978-4-7857-2200-5
定価:3,300円 (本体3,000円+税)
発売日:2014年07月
在庫:在庫あり
詳細
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)」が平成25年12月に公布された。同法は消費者の利益を擁護する一方、ひとたび訴訟となれば、企業に多大な影響を与える。本書は、立案担当者が、立法の背景・経緯のほか、制度に関する基本的な論点を解説。
主要目次
Q1 本制度創設の経緯及び目的はどのようなものですか。
Q2 本制度の概要はどのようなものですか。
Q3 二段階型の手続としたのはなぜですか。
Q4 共通義務確認訴訟において消費者からの授権を要しないとしたのはなぜですか。
Q5 諸外国の状況はどのようなものですか。
Q6 米国のクラス・アクションと本制度はどのような違いがありますか。
Q7 過去の消費者事件のうち、どのような事案が本制度の対象になりますか。
Q8 本制度は悪質商法事案にも有効に機能するものとなっていますか。
Q9 本制度において不当な訴訟を抑止するためにどのような措置を講じていますか。
Q10 本制度の導入による日本経済への影響はどのようなものですか。
Q11 「消費者」、「事業者」及び「消費者契約」(第2条第1号から第3号まで)とはどのようなものですか。
Q12 「相当多数」(第2条第4号)とは、どのくらいの人数をいうのですか。
Q13 「消費者に共通する事実上及び法律上の原因」(第2条第4号)とはどのようなものですか。
Q14 「個々の消費者の事情によりその金銭の支払請求に理由がない場合」(第2条第4号)とはどのようなものですか。
Q15 損害額の算定方法について確認を求めることはできますか。
Q16 「対象債権」及び「対象消費者」(第2条第5号・第6号)とはどのようなものですか。
Q17 訴えられる請求金額に上限を設けなかったのはなぜですか。
Q18 リコールなど事業者が自主的な対応をしている場合にはどのような配慮がされていますか。
Q19 対象となる請求(第3条第1項)を規定するに当たっての考え方はどのようなものですか。
Q20 消費者契約に関する「不当利得に係る請求」(第3条第1項第2号)とはどのようなものですか。
Q21 消費者契約に関する「不法行為に基づく損害賠償の請求」について、
民法の規定によるものに限っている(第3条第1項第5号)のはなぜですか。
Q22 いわゆる拡大損害、人身損害、逸失利益、慰謝料については本制度を利用して
請求することができないとしている(第3条第2項)のはなぜですか。
Q23 法人である事業者の代表者などの個人を被告とすることができないのはなぜですか。
Q24 不法行為に基づく損害賠償の請求について、契約当事者ではない勧誘をする事業者等も
被告とすることができるとしている(第3条第3項第2号)のはなぜですか。
Q25 広告宣伝活動を行った事業者は勧誘をする事業者(第3条第3項第2号)に当たりますか。
Q26 「勧誘を助長する事業者」(第3条第3項第2号)とはどのようなものですか。
Q27 「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが
困難であると認めるとき」(第3条第4項)とはどのようなものですか。
Q28 「共通義務確認の訴えの全部又は一部を却下することができる。」
(第3条第4項)とありますが、却下するか否かについて裁判所に裁量がありますか。
Q29 共通義務確認の訴えは特定適格消費者団体のみが訴えられるとしているのはなぜですか。
Q30 共通義務確認の訴えを財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなした(第4条)のはなぜですか。
Q31 「対象債権及び対象消費者の範囲」(第5条)は、どの程度特定されている必要がありますか。
Q32 商品の品質に問題があるとしても、実際に不具合が生じている消費者と
生じていない消費者がいる場合に、対象消費者の範囲の設定はどのようにすべきですか。
Q33 共通義務確認の訴えの管轄はどのようなものですか。
Q34 共通義務確認の訴えの国際裁判管轄はどのようなものですか。
Q35 請求の内容及び相手方が同一である共通義務確認の訴えについて、複数の特定適格消費者団体に
よってそれぞれ異なる裁判所に提起された場合の取扱いはどのようなものですか。
Q36 事実上及び法律上同種の原因に基づく請求を目的とする共通義務確認の訴えについて、
それぞれ異なる裁判所に提起された場合の取扱いはどのようなものですか。
Q37 消費者が特定適格消費者団体を補助するため、補助参加をすることができないのはなぜですか。
Q38 共通義務確認訴訟の確定判決の効力はどのようなものですか。
Q39 共通義務確認訴訟の確定判決の効力を届出消費者や当事者以外の特定適格消費者団体にも及ぼすのはなぜですか。
Q40 共通義務確認訴訟の請求棄却判決が確定した場合にはどのような効力がありますか。
Q41 共通義務確認訴訟の判決に対しては上訴をすることができますか。
Q42 共通義務確認訴訟ですることができる訴訟上の和解及びできない訴訟上の和解はどのようなものですか。
Q43 特定適格消費者団体は、裁判外の和解をすることができますか。
Q44 共通義務確認訴訟における訴訟上の和解にはどのような効力がありますか。
Q45 対象消費者の権利を害する目的をもってされる和解の防止策及び是正手段はどのようなものですか。
Q46 共通義務確認訴訟の係属中に被告が破産した場合はどのように取り扱われますか。
Q47 対象債権の確定手続の概要はどのようなものですか。
Q48 特定適格消費者団体は簡易確定手続開始の申立てをしなければならないとしている(第14条)のはなぜですか。
Q49 「正当な理由」(第14条)とはどのようなものですか。
Q50 簡易確定手続開始の申立ての取下げにはどのような規律がありますか。
Q51 簡易確定手続はどのくらいの期間を要すると考えられますか。
Q52 簡易確定手続において届出を促すための方策はどのようなものですか。
Q53 「正当な理由」(第25条第1項、第26条第1項)とはどのようなものですか。
Q54 「知れている対象消費者」(第25条第1項)とはどのようなものですか。
Q55 「相当な方法」(第26条第1項)とはどのようなものですか。
Q56 通知・公告の費用は誰が負担するのですか。
Q57 通知・公告の費用を特定適格消費者団体が負担するのはなぜですか。
Q58 相手方に公表義務や情報開示義務を課すのはなぜですか。
Q59 相手方はどのような方法で公表(第27条)する必要がありますか。
Q60 相手方が情報開示義務を負う文書はどのようなものですか。
Q61 「開示すべき文書の範囲を特定するために不相当な費用又は時間を要するとき」
(第28条第1項ただし書)とはどのようなものですか。
Q62 情報開示命令の実効性はどのように確保されているのですか。
Q63 情報開示の求めに応じて相手方が開示した文書に記載のあった消費者について、
相手方は後に対象消費者ではないと争うことができますか。
Q64 相手方が第三者に顧客管理を委託している場合に、情報開示義務を負うことがありますか。
Q65 相手方が情報開示義務に基づいて申立団体に情報を開示することは、個人情報の保護に関する
法律第23条が禁止する個人データの第三者提供には当たりませんか。
Q66 情報開示の求めがあった後に、相手方が文書を破棄した場合には、情報開示義務に違反することになりますか。
Q67 簡易確定手続はどのような点が簡易なものとなっていますか。
Q68 簡易確定手続において届出をすることができる債権はどのようなものですか。
Q69 同一の債権について別に訴訟が係属している場合に債権届出をすることはできますか。
Q70 債権届出をしなかった場合には、消費者の権利にはどのような影響がありますか。
Q71 債権届出及び簡易確定手続を追行するための授権(第31条第1項)には、事業者からの弁済受領権限が含まれますか。
Q72 「授権を欠いたとき」(第31条第6項)に債権届出の取下げがあったものとみなすのはなぜですか。
Q73 簡易確定決定があった後に、授権を取り消したときは、更に授権をすることができない
(第31条第9項)としているのはなぜですか。
Q74 簡易確定手続申立団体は、授権をしようとする者に対して、授権に先立ちどのような事項を
説明しなければならないのですか。
Q75 簡易確定手続申立団体は、やむを得ない理由があるときを除いて、授権を拒むことができない
(第33条第1項)としているのはなぜですか。
Q76 「やむを得ない理由」(第33条第1項、同条第2項)とはどのようなものですか。
Q77 簡易確定手続申立団体の公平誠実義務とはどのようなものですか。
Q78 簡易確定手続申立団体の善管注意義務とはどのようなものですか。
Q79 時効の中断についてはどのような特則がありますか。
Q80 債権届出団体は、届出期間内に限り、債権届出の内容を変更することができる(第39条)としたのはなぜですか。
Q81 債権届出の取下げについてはどのような規律がありますか。
Q82 債権届出の認否についてはどのような規律がありますか。
Q83 債権届出団体は、認否を争う旨の申出(第43条第1項)や異議の申立て(第46条第1項)に際して、
届出消費者にどのように説明をする必要がありますか。
Q84 簡易確定決定のための審理において、証拠調べを書証に限った(第45条第1項)のはなぜですか。
Q85 簡易確定決定の効力はどのようなものですか。
Q86 簡易確定決定において請求が棄却された場合には消費者の権利にはどのような影響がありますか。
Q87 簡易確定手続の係属中に相手方が破産した場合にはどのように取り扱われますか。
Q88 簡易確定手続の費用の負担はどのように規律されていますか。
Q89 簡易確定手続開始の申立ての手数料はどのように規律されていますか。
Q90 債権届出の手数料はどのように規律されていますか。
Q91 簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあったときは、原告はどのように定まりますか。
Q92 訴えの提起があったものとみなされた場合(第52条第1項)の訴えの提起の手数料は、
だれが支払うことになりますか。
Q93 「正当な理由があるとき」(第53条第4項、同条第5項)とはどのようなものですか。
Q94 異議後の訴訟において「授権を欠くとき」(第53条第9項)はどのように取り扱われますか。
Q95 異議後の訴訟において訴えの変更が制限され、反訴が禁止される(第54条)のは、なぜですか。
Q96 異議後の訴訟において、いわゆる拡大損害等の対象とならない損害について請求することができますか。
Q97 異議後の訴訟は個別の訴訟と併合することができますか。
Q98 異議後の訴訟の係属中に相手方が破産した場合にはどのように取り扱われますか。
Q99 特定適格消費者団体のする仮差押え(第56条第1項)の手続はどのようなものですか。
Q100 「当該特定適格消費者団体が取得する可能性のある債務名義に係る対象債権の総額」
(第56条第3項)はどのように明らかにすることになりますか。
Q101 仮差押命令の担保はどのようになりますか。
Q102 事業者は特定適格消費者団体のする仮差押えについてどのように争い、
また、被った損害の賠償をどのように求めることができますか。
Q103 特定適格消費者団体のする仮差押えをした場合どのように被害回復をすることができますか。
Q104 特定認定が失効し又は取り消されたときに被害回復裁判手続はどのような影響を受けますか。
Q105 共通義務確認訴訟が係属する場合に、同一の被告と消費者との間の個別の訴訟にはどのような影響がありますか。
Q106 債権届出団体は、強制執行をする場合には、届出消費者から改めて授権を得る必要はありますか。
Q107 本制度の手続追行主体を内閣総理大臣が認定することとしたのはなぜですか。
Q108 適格消費者団体とはどのようなものですか。
Q109 適格消費者団体の認定要件はどのようなものですか。
Q110 適格消費者団体の活動状況はどのようなものですか。
Q111 特定適格消費者団体の要件はどのようなものですか。
Q112 特定適格消費者団体の要件は適格消費者団体の要件と比べどのような点が付加されていますか。
Q113 特定認定の要件として、差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを
定めているのはなぜですか。
Q114 被害回復関係業務を適正に遂行するに足りる組織体制・経理的基礎とはどのようなものですか。
Q115 弁護士を理事に選任し、弁護士に手続を追行させなければならないのは、なぜですか。
Q116 「不当な目的でみだりに」(第75条第2項)とはどのようなものですか。
Q117 特定適格消費者団体が報酬の支払を受けることができることとしたのはなぜですか。
Q118 特定適格消費者団体は、(事業者から)寄附を受けることができますか。
Q119 特定適格消費者団体として支払を受けた報酬又は費用を差止請求関係業務の費用に充てることはできますか。
Q120 特定適格消費者団体の個人情報の取扱いについてはどのような規律がありますか。
Q121 特定適格消費者団体の適格性に疑義がある場合には是正を求めたい者はどのようなことができますか。
Q122 共通義務確認訴訟の判決を消費者庁はどのように周知するのですか。
Q123 公布の日から起算して3年を超えない範囲内で施行するのはなぜですか。
Q124 施行前の事案について本制度の適用をしない(附則第2条)のはなぜですか。
Q125 不法行為については加害行為を基準とし、その他の請求については契約を基準としているのはなぜですか。
Q126 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正(附則第9条)についてはどのようなことを定めていますか。
Q127 民事執行法の一部改正(附則第10条)についてはどのようなことを定めていますか。
Q128 消費者契約法の一部改正(附則第11条)についてはどのようなことを定めていますか。
