- トップ
- 一問一答 被災借地借家法・改正被災マンション法
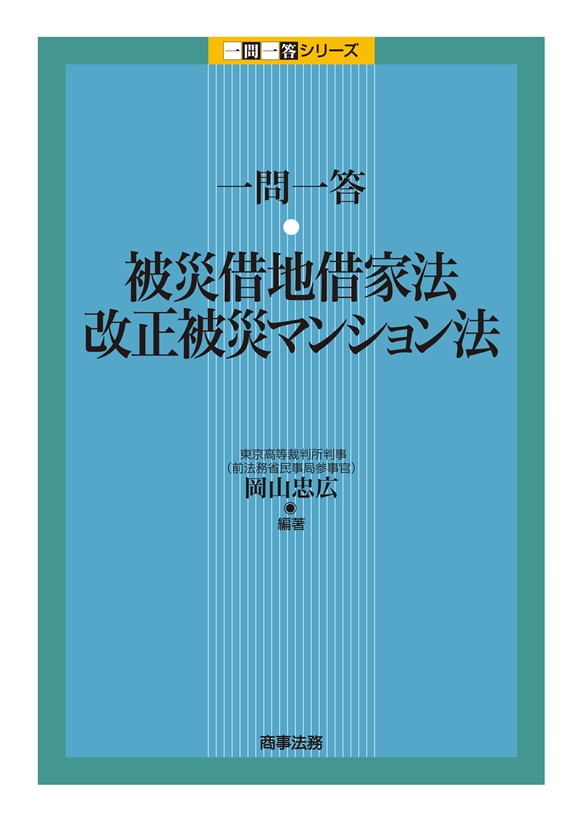
詳細
平成25年6月26日に公布された「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」および「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部を改正する法律」について、立案担当者が、その経緯、内容についてわかりやすく解説。
主要目次
平成25年6月26日に公布された「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法」および「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第1部 被災借地借家法 第1編 総 論 Q1 新法はどのようなことを定めていますか。 Q2 新法の制定経緯はどのようなものですか。 Q3 旧法にはどのような問題点があったのですか。また、新法の制定に伴い、旧法はどうなったのですか。 Q4 旧法を改正するのではなく、新法を制定することとしたのはなぜですか。 Q5 建物の「滅失」とはどのような状態をいうのですか。 第2編 各 論 [第2条関係] Q6 新法は、どのような災害に適用されますか。 Q7 新法において、適用すべき措置及びこれを適用する地区を政令で指定することとしたのはなぜですか。 Q8 新法を適用する旨の政令が定められた後、適用すべき措置や地区が追加して指定されることはありますか。 また、追加指定がされた場合には、当該措置は、いつまで適用されることになりますか。 [第3条関係] Q9 災害により建物が滅失した場合に、借地権者による借地契約の解約を認めることとしたのはなぜですか。 Q10 借地契約の解約等の特例を認める期間を1年間としたのはなぜですか。 Q11 借地契約の解約等の特例において、借地権は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった 日から3か月を経過することによって消滅するとしたのはなぜですか。 [第4条関係] Q12 借地権が設定された土地が第三者に売却された場合に、借地権者は、土地を買い受けた第三者に借地権を 主張することができますか。 Q13 借地権の対抗力の特例を認めることとしたのはなぜですか。 Q14 掲示をすることなく借地権の対抗力を認める期間(第4条第1項)を政令の施行の日から起算して6か月間 としたのはなぜですか。 Q15 掲示によって借地権の対抗力を認める期間を3年間としたのはなぜですか。 Q16 第4条第2項の掲示においては、どのような事項を掲示する必要がありますか。 Q17 借地権の対抗力の特例に関する措置(第4条)が政令で指定される前に、借地権の目的である土地が売買さ れた場合には、借地権者は、その土地の買受人に借地権を対抗することはできますか。 Q18 借地権の対抗力の特例に関する措置が政令で指定される前に、借地権者が借地借家法第10条第2項の掲 示をしていた場合には、借地権の対抗力はどうなるのですか。改めて掲示をしなおさなければならないので すか。 Q19 第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合について、民法第533条、 第566条第1項及び第3項の各規定を準用(第4条第3項、第4項)しているのはなぜですか。 [第5条関係] Q20 借地上の建物が災害により滅失した場合に、借地権者の申立てにより、裁判所が、土地の賃借権の譲渡又は 転貸について、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができるものとしたのはなぜですか。 Q21 第三者が土地の賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に「不利となるおそれ」がないかどうかは どのように判断されるのですか。また、この判断に当たっては、再築される建物がどのようなものかという ことも考慮されるのですか。 Q22 土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるとき は、裁判所は、賃借権の譲渡又は転貸について財産上の給付に係らしめることができるとされていますが、 その給付額はどのようにして定まるのですか。 Q23 第5条第2項において、借地借家法第19条第2項から第6項まで及び第4章の規定が準用されていますが、 それぞれどのようなことが定められているのですか。 Q24 土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可の特例を認める期間を政令の施行の日から起算して1年間としたの はなぜですか。 [第7条関係] Q25 被災地において短期の借地権(被災地短期借地権)の設定を可能とする制度を創設することとしたのはなぜ ですか。 Q26 被災地短期借地権は、どのような借地権ですか。契約の更新等の借地借家法の規定の適用はありますか。 Q27 被災地短期借地権の設定可能期間を政令施行の日から起算して2年間としたのはなぜですか。 Q28 被災地短期借地権の存続期間の上限を5年としたのはなぜですか。 Q29 被災地短期借地権の存続期間が満了した場合、借地上に建てられた建物はどうすればよいですか。 Q30 被災地短期借地権の存続期間が満了した後も、借地関係を継続するためにはどうすればよいですか。 Q31 被災地短期借地権の設定を目的とする契約を、公正証書による等書面によってしなければならないものとし たのはなぜですか。 Q32 被災地短期借地権は、借地借家法第25条の一時使用目的借地権とどのような点で異なるのですか。 [第8条関係] Q33 従前の賃借人に対する通知制度とは、どのような制度ですか。 Q34 災害により建物が滅失した後、従前の賃貸人が建物を再築して賃貸しようとする場合に、従前の賃借人に対 してその旨を通知することとしたのはなぜですか。 Q35 従前の賃借人に対する通知制度(第8条)においては、誰が通知をしなければなりませんか。 Q36 災害により建物が滅失したことを契機に従前とは全く異なる用途の建物を再築する場合にも、従前の賃借人 に対して通知をしなければならないのですか。 Q37 従前の賃借人に対する通知制度において、従前の賃貸人は、いつ通知をしなければならないのですか。 Q38 従前の賃借人に対する通知制度において、従前の賃貸人は、誰に対して通知をしなければならないのです か。 Q39 従前の賃借人に対する通知をしなければならない期間を3年間としたのはなぜですか。 Q40 従前の賃借人に対する通知を怠った場合にはどうなりますか。 [附則関係] Q41 旧法の廃止により、旧法の規定により形成された法律関係について影響はありますか。 第2部 改正被災マンション法 第1編 総 論 Q1 旧法が制定された背景事情は、どのようなものですか。 Q2 今回の改正に至る経緯は、どのようなものですか。 Q3 改正法では、どのようなことを定めていますか。 Q4 改正法と区分所有法とはどのような関係にあるのですか。 Q5 「全部滅失」、「大規模一部滅失」の意味は何ですか。 Q6 「全部滅失」、「大規模一部滅失」は、誰がどのように判断するのですか。 Q7 改正法は、どのような災害に適用されますか。 Q8 改正法は、東日本大震災に適用されますか。 Q9 改正法で設けられた建物敷地売却決議や取壊し決議といった措置は、被災時に限らず、老朽化マンション対 策として必要ではないですか。 第2編 各 論 第1章 総 則 [第1条関係] Q10 改正法の目的は何ですか。 第2章 区分所有建物が全部滅失した場合における措置 Q11 改正法第2章では、どのようなことを定めていますか。 Q12 「敷地共有持分等」、「敷地共有者等」、「敷地共有者等集会」とは、それぞれどのような意味ですか。 [第2条関係] Q13 第2条はどのようなことを定めていますか。 Q14 「政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合」に「政令で定める災害により区分所有建物 が大規模一部滅失した場合において、当該区分所有建物が取壊し決議(第11条)又は区分所有者全員の同意 に基づき取り壊されたとき」を含めているのはなぜですか。 Q15 改正法第2章で定める措置には、どのような期間制限が設けられていますか。 [第3条関係] Q16 第3条第1項はどのようなことを定めていますか。 Q17 第3条第1項で区分所有法の規約に関する規定を準用していない理由は何ですか。 Q18 敷地共有者等集会の手続の概略はどのようなものですか。 Q19 敷地共有者等が所在不明となっている場合、敷地共有者等集会を招集するためにはどのようにすればよい のですか。 Q20 敷地共有者等の「所在を知ることができないとき」とは、どのような場合ですか。 Q21 敷地共有者等に対する集会の招集の通知に代えて掲示によって集会の招集を通知する場合、敷地共有者等 集会を招集する者は、敷地共有者等の所在を確認するためにどのような調査を行わなければなりませんか。 [第4条関係] Q22 再建決議制度について改正をした理由は何ですか。また、どのような改正がされたのですか。 Q23 再建決議について敷地共有者等の議決権の5分の4以上という決議要件について変更を加えなかったの は、なぜですか。 Q24 再建決議をするための敷地共有者等集会の手続の概略は、どのようになっていますか。 Q25 再建決議においてはどのような事項を定めなければなりませんか。 Q26 再建決議のための集会を招集する場合には、どのような事項を通知する必要がありますか。 Q27 再建決議のための敷地共有者等集会の前に開催される説明会においては、誰が、何を行う必要があります か。 Q28 再建決議があった場合、決議に賛成しなかった者に対する売渡請求権を行使するための手続の概略は、ど のようになっていますか。 Q29 売渡請求権が行使されると、当事者間にどのような法律関係が生じるのですか。 Q30 売渡請求権が行使された場合における「時価」とはどのようにして定められるものですか。 Q31 再建は、誰がどのようにして実行するのですか。 Q32 再建決議がされたのに、再建が行われない場合はどうなるのですか。 Q33 再建決議がされた場合、全部滅失した区分所有建物の敷地利用権について抵当権を有していた者の権利は どうなるのですか。 [第5条関係] Q34 敷地売却決議制度を創設した理由は何ですか。 Q35 敷地売却決議に議決権の5分の4以上の多数を要求した理由は何ですか。 Q36 敷地利用権が賃借権や地上権など所有権以外の権利であった場合であっても、敷地売却決議をすることは できますか。 Q37 敷地売却決議の手続の概要はどのようなものですか。 Q38 敷地売却決議においては、どのような事項を定めなければなりませんか。 Q39 敷地売却決議において、売却代金の分配に関する事項を決議事項としていないのはなぜですか。 Q40 敷地売却決議をするための集会を招集する場合には、どのような事項を通知する必要がありますか。 Q41 敷地売却決議のための敷地共有者等集会の前に開催される説明会においては、誰が、何を行う必要があり ますか。 Q42 敷地売却決議があった場合、決議に賛成しなかった者に対する売渡請求権を行使するための手続の概略 は、どのようになっていますか。また、売渡請求権が行使されると、当事者間にどのような法律関係が生じ るのですか。 Q43 敷地の売却は、誰がどのようにして実行するのですか。 Q44 敷地売却決議がされたのに売却が行われない場合は、どうなるのですか。 Q45 敷地売却決議がされた場合、全部滅失した区分所有建物の敷地利用権について抵当権を有していた者の権 利はどうなるのですか。 [第6条関係] Q46 区分所有建物が全部滅失した場合に、一定期間、敷地共有者等による共有物の分割の請求を制限している のはなぜですか。 Q47 敷地共有者等による共有物の分割の請求が禁止されるのは、いつからですか。 Q48 共有物の分割が禁止されている期間、敷地共有者等の法律関係はどうなるのですか。 Q49 再建決議や敷地売却決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合には、分割禁止期間中で あっても共有物の分割の請求を許容することとしたのはなぜですか。 Q50 再建決議及び敷地売却決議をすることができない顕著な事由がある場合とは、どのような場合ですか。 Q51 分割禁止期間中に第6条第1項ただし書又は第2項ただし書に定める顕著な事由があるとして分割がされ、 その後においてなお建物の敷地又はこれに関する権利を数人が有する状態が続く場合、その敷地共有者等 は、再建決議や敷地売却決議をすることができますか。 第3章 区分所有建物の一部が滅失した場合における措置 [第3章総論] Q52 区分所有建物が大規模一部滅失した場合には、どのような措置をとることができますか。 Q53 改正法第3章では、どのようなことを定めていますか。 Q54 改正法において、区分所有建物が大規模一部滅失した場合における措置を設けたのはなぜですか。 Q55 大規模一部滅失に至らない区分所有建物を改正法の適用対象としなかったのはなぜですか。 [第7条関係] Q56 区分所有建物が大規模一部滅失した場合における措置として、区分所有者集会の特例(第7条)を設け ることにしたのはなぜですか。 Q57 改正法第3章で定める措置には、どのような期間制限が設けられていますか。 [第8条関係] Q58 区分所有建物が大規模一部滅失した場合について、区分所有者集会の招集の通知に関する特例を設ける ことにしたのはなぜですか。 Q59 区分所有建物が大規模一部滅失した場合に、区分所有者集会を招集しようとする者は、どのように招集の通 知をするのですか。 [第9条から第11条関係] Q60 建物敷地売却決議制度、建物取壊し敷地売却決議制度及び取壊し決議制度を設けることにしたのはなぜで すか。 Q61 建物敷地売却決議及び建物取壊し敷地売却決議の多数決の基準として区分所有者、議決権に加えて敷地 利用権の持分の価格を考慮しているのはなぜですか。取壊し決議においては敷地利用権の持分の価格を考慮 していないのはなぜですか。 Q62 建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議及び取壊し決議に5分の4以上の多数を要求したのはなぜで すか。 Q63 敷地利用権が賃借権や地上権など所有権以外の権利であった場合でも、建物敷地売却決議及び建物取壊 し敷地売却決議をすることはできますか。 Q64 建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議及び取壊し決議の手続の概略は、それぞれどのようになっ ていますか。 Q65 建物敷地売却決議においては、どのような事項を定めなければなりませんか。 Q66 建物敷地売却決議における、売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関 する事項について、各区分所有者の衡平を害しない定め方とは、どのような定め方ですか。 Q67 建物敷地売却決議をするための集会を招集する場合には、どのような事項を通知する必要がありますか。 Q68 建物敷地売却決議における「売却を必要とする理由」として、どのような事項を通知する必要があります か。 Q69 建物敷地売却決議において、「建替えに要する費用の概算額」が通知事項とされていないのは、なぜです か。 Q70 建物敷地売却決議をするための区分所有者集会の前に開催される説明会においては、誰が、何を行う必要 がありますか。 Q71 建物敷地売却決議があった場合、決議に参加しない区分所有者は、どのように扱われますか。 Q72 建物敷地売却決議が成立した後に、売渡請求権が行使された場合の「時価」は、どのようにして定められま すか。 Q73 建物敷地売却決議が成立した後、建物及びその敷地の売却は、誰がどのようにして実行するのですか。 Q74 建物敷地売却決議がされたのに、売却が行われない場合は、どうなるのですか。 Q75 建物敷地売却決議がされた場合、区分所有権及び敷地利用権に抵当権を有していた者の権利はどうなるの ですか。 Q76 建物敷地売却決議がされた場合、区分所有建物を賃借していた賃借人はどうなるのですか。 Q77 建物取壊し敷地売却決議においては、どのような事項を定めなければなりませんか。 Q78 建物取壊し敷地売却決議における建物の取壊しに要する費用の分担について、各区分所有者の衡平を害しな い定め方とは、どのような定め方ですか。 Q79 建物取壊し敷地売却決議をするための集会を招集する場合には、どのような事項を通知する必要があります か。 Q80 建物取壊し敷地売却決議における「区分所有建物の取壊し及びこれに係る建物の敷地の売却を必要とする 理由」として、どのような事項を通知する必要がありますか。 Q81 建物取壊し敷地売却決議において通知すべき事項として「建替えに要する費用の概算額」 が規定されていな いのは、なぜですか。 Q82 建物取壊し敷地売却決議をするための区分所有者集会の前に開催される説明会は、誰が、何を行う必要 がありますか。 Q83 建物取壊し敷地売却決議があった場合、決議に参加しない区分所有者は、どのように扱われますか。 Q84 建物取壊し敷地売却決議がされた後に売渡請求権が行使された場合の「時価」は、どのようにして定められ ますか。 Q85 建物の取壊し及びその敷地の売却は、誰がどのようにして実行するのですか。 Q86 建物取壊し敷地売却決議がされたのに、取壊しが行われない場合は、どうなるのですか。また、建物が取り 壊されたのに、その敷地が売却されない場合はどうですか。 Q87 建物取壊し敷地売却決議がされた場合、区分所有建物及び敷地利用権に抵当権を有していた者の権利はど うなるのですか。 Q88 建物取壊し敷地売却決議がされた場合、区分所有建物を賃借していた賃借人はどうなるのですか。 Q89 取壊し決議においては、どのような事項を定めなければなりませんか。 Q90 建物の取壊しに要する費用の分担について、各区分所有者の衡平を害しない定め方とは、どのような定め方 ですか。 Q91 取壊し決議をするための集会を招集する場合には、どのような事項を通知する必要がありますか。 Q92 取壊し決議における「取壊しを必要とする理由」として、どのような事項を通知する必要がありますか。 Q93 通知すべき事項として「建替えに要する費用の概算額」が規定されていないのは、なぜですか。 Q94 取壊し決議をするための区分所有者集会の前に開催される説明会は、誰が、何を行う必要がありますか。 Q95 取壊し決議があった場合、決議に参加しない区分所有者は、どのように扱われますか。 Q96 取壊し決議がされた後に売渡請求権が行使された場合の「時価」は、どのようにして定められますか。 Q97 建物の取壊しは、誰がどのようにして行うのですか。 Q98 取壊し決議がされたのに、取壊しが行われない場合は、どうなるのですか。 Q99 取壊し決議がされた場合、区分所有建物に抵当権を有していた者の権利はどうなるのですか。 Q100 取壊し決議がされた場合、区分所有建物を賃借していた賃借人はどうなるのですか。 [第12条関係] Q101 大規模な災害により区分所有建物が大規模一部滅失した場合に、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売 却決議取壊し決議及び一括建替え等決議がいずれも成立しなかったときは、どうなるのですか。 第4章 団地内の建物が滅失した場合における措置 [団地総論] Q102 区分所有法上、団地とはどのようなものを指しますか。 Q103 団地内の建物が滅失した場合における措置には、どのようなものがありますか。 Q104 改正法において、団地内の建物が滅失した場合における措置を設けたのはなぜですか。 Q105 団地内の建物が滅失した場合における措置が適用されるのは、どのような団地ですか。 Q106 団地内の建物が滅失した場合における措置が適用される期間を3年間としたのはなぜですか。 [第13条、第14条関係] Q107 団地内の建物が滅失した場合における管理者及び集会に関する規律を設けることにしたのはなぜですか。 Q108 団地建物所有者等集会の構成員となるのは、どのような人ですか。「団地建物所有者等」とはどのような人 のことをいうのですか。 Q109 改正法の団地建物所有者等集会と区分所有法上の団地の集会とは、どのような関係にありますか。 Q110 団地建物所有者等が置く管理者や団地建物所有者等に関して準用される区分所有法の規定には、どのよ うなものがありますか。また、敷地共有者等集会と異なる点は、どのような点ですか。 Q111 第14条第1項において準用する区分所有法の規定の読替えはどのようなことを定めているのですか。 Q112 団地建物所有者等の所在が分からない場合には、どのようにして集会を招集すればよいのですか。 Q113 再建承認決議制度を設けることにしたのはなぜですか。 Q114 団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議制度を設けることにしたのはなぜですか。 Q115 建替え再建承認決議制度を設けることにしたのはなぜですか。 Q116 再建承認決議等の多数決要件を4分の3以上としているのはなぜですか。従前と同一規模の建物を再建 する場合でも4分の3以上の承認が必要なのですか。団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議 や建替え再建承認決議についてはどうですか。 Q117 再建承認決議を行う場合の議決権の割合は、どのように計算するのですか。団地内の建物が滅失した場合 における建替え承認決議や建替え再建承認決議についてはどうですか。 Q118 再建承認決議を行う場合の手続はどのようなものですか。再建決議の手続とは、どのような点で異なります か。 建替え承認決議や建替え再建承認決議についてはどうですか。 Q119 再建決議をした建物に係る敷地共有者等について、再建承認決議に賛成する旨の議決権を行使したもの とみなすこととしたのはなぜですか。建替え承認決議や建替え再建承認決議についてはどうですか。 Q120 建物の再建によって、団地内の他の建物の将来の建替えや再建が制約される場合、その建物の区分所有 者や敷地共有者等の利益は、どのようにして保護されるのですか。団地内の建物が滅失した場合における建 替え承認決議の場合や建替え再建承認決議の場合についてはどうですか。 (以下、略)
